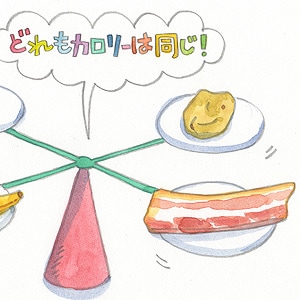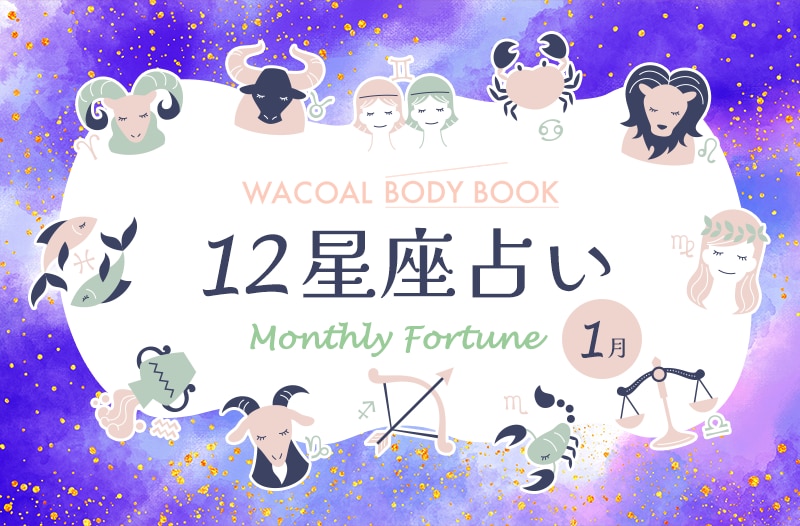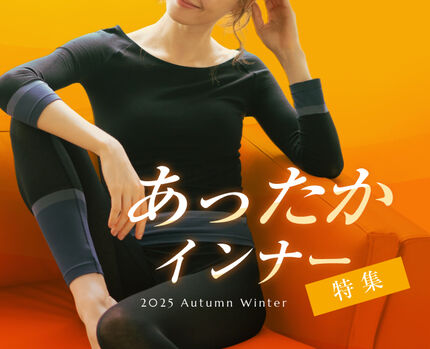新社会人にとって、緊張感とワクワク感の高まる新年度! 新しいスーツに合わせて新しいパンプスを、と考えている方もいるのではないでしょうか。ところが、スニーカー生活に慣れた足に、パンプスはツラい…と感じることも事実。なぜ、このようなことが起こるのか。どうしたら、パンプスを履いたときのトラブルを防げるのか。
ワコールのパンプス「サクセスウォーク」の開発にも携わっている阿部 薫教授に、現代女性の足事情とあわせてお話しいただきました。
現代女性の足は「細く」「薄く」
なっている!?
――まず、現代に生きる私たちの足は、過去と比較して何か変化しているのでしょうか?
「足の大きさ、つまり足の骨格は、女性では11歳くらいまでにほぼ完成するといわれています。小学5〜6年生で23センチの靴を履いていた人は、それ以降のサイズは大きく変わらず、大人になっても変わらず23センチということが多いわけです。
骨格の完成は、子どものころの運動がカギになります。かけっこ、野球、サッカー…と、足を使って遊んでいたら丈夫に育つのですが、男子に比べて女子のほうがインドアの遊びが多いうえ、今ではひとり一台のゲーム時代。それが、足の発達を阻害してしまっているのです。
今の20代、30代は、小学生のときからゲーム世代でしたから、それ以前と比べれば、運動量が減っているのは明らかです。その結果、現代人の足は、足長はかつてと大きく変わらないものの、足幅が狭くなっているのが特徴です。私が大学生の足を測定した際には、標準的な靴の足幅は「E」ですが、それより細い「D」「C」がほぼ同じ数いました。

――となると、足に合う靴も変わってきそうですが…。
ところが、一般に販売されている靴の木型(靴をつくる際に使用される元型)は、何十年もずっと同じものが使われています。サイズごとに異なるすべての木型をつくりかえるのは、大きな投資が必要になってしまうからなのですが、多くの場合、木型はかつてのままで、そこに載せるデザインを変えて、新しい靴を提供しているのが現状です。
ただメーカーによっては、細く木型をつくって履きやすさを工夫しているところもあります。ワコールでも、かかとが小さい女性のために新しいパンプスをつくりました。現代の女性の足にフィットする靴のためには、これまでの業界の習慣から見直す必要があるといえそうです。
 ワコール「サクセスウォーク」で使用している木型(イメージ)。現代女性の足にフィットする木型を開発している
ワコール「サクセスウォーク」で使用している木型(イメージ)。現代女性の足にフィットする木型を開発している
弱くなった筋肉を補う
パンプスを選ぼう
――それでも、TPOによってはパンプスを履きたいこともあります。どうしたらよいのでしょう?
いざ履こうと思っても、日常生活での運動量も減っていると筋力不足になり、きちんと歩くことができません。筋力がないのにパンプスを無理して履くと、途端にあちこち筋肉痛になってしまいます。コロナ明けに久しぶりにパンプスを履いたら、足がガクガクして歩けなかった、とても疲れた、なんていう体験をした方も多いのではないでしょうか。
かといって、パンプスを履くために筋トレするというのも、現実的ではないですよね。そんなときには、歩く動作をサポートしてくれる靴を選べばいいんです。たとえば、土踏まずの部分をサポートするインソールがついているもの、適度にやわらかくて指の付け根が曲がりやすいもの、そしてかかとがしっかりホールドされるもの、など。大事なのは、<自分の足の特徴に合った靴>と、<歩行をサポートする機能のあるもの>を選ぶ、ということです。
 足裏の形状に合わせて設計された3D形状により、足裏にかかる負担を分散する、サクセスウォークのインソール
足裏の形状に合わせて設計された3D形状により、足裏にかかる負担を分散する、サクセスウォークのインソール
――スーツのときでも、パンプスではなくスニーカーを履くことも一般的になりました。特に最近は厚底スニーカー流行りですが、歩く際の注意点はありますか?
スニーカーならなんでもからだにいい、という認識をもっている方がいますが、それは間違いです。スニーカーには、短距離用と長距離用とあり、短距離用は足を固定するので、日常に履くのには適していません。長距離用、すなわち厚底タイプのほうが向いているわけですが、これにも注意が必要です。
厚底スニーカーは上げ底のぶん脚長効果が期待できますが、足関節の位置が高くなるぶん外側に転倒する確率が高くなります。これで転倒すると、普通の靴で転んだときより、靭帯(じんたい)破損の程度が大きくなるので、注意してください。そうならないためには、歩行で着地のとき、足裏全体でまっすぐに着地すること。ほかの靴と同様にかかとから着地すると、かえって危険です。雪の上で転ばないように歩くとき、足裏全体で着地する歩き方と同じですね。
<後半>では、働く女性の日常シーンごとのパンプスの選び方を指南いただきます。さらに、足トラブルの対処法などもご紹介。お楽しみに! 3月12日更新予定
-

- 阿部 薫(あべ かおる) 新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健学専攻義肢装具自立支援学分野長(博士後期課程・修士課程)/リハビリテーション部義肢装具自立支援学科・教授。同大学院にて、靴とヒトの関係を科学的に研究する「靴人間科学」を担当している。
デザイン/WATARIGRAPHIC