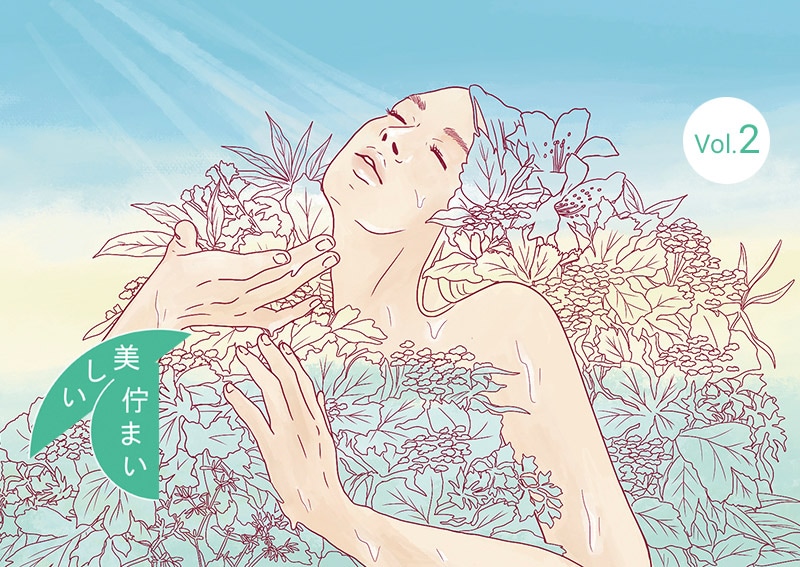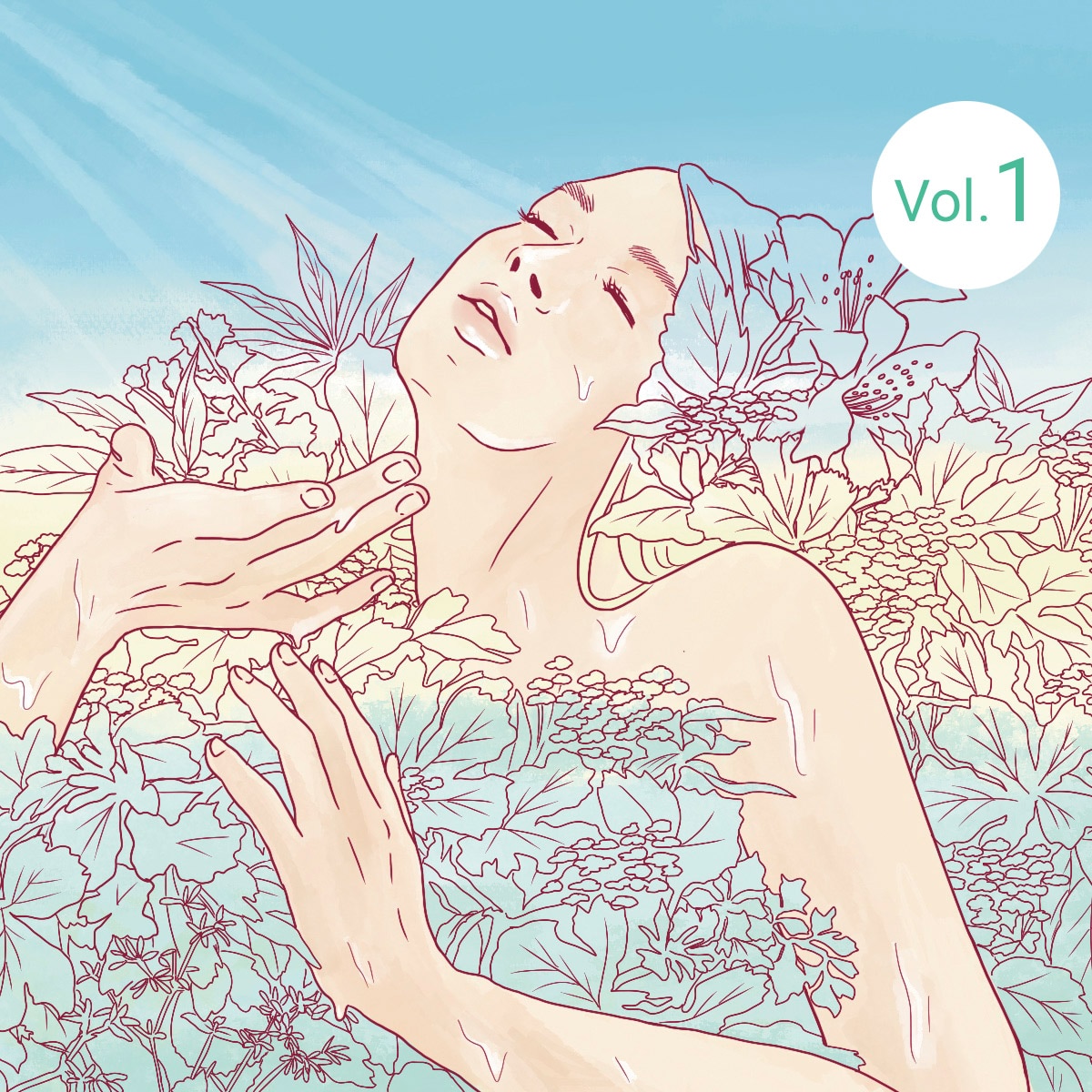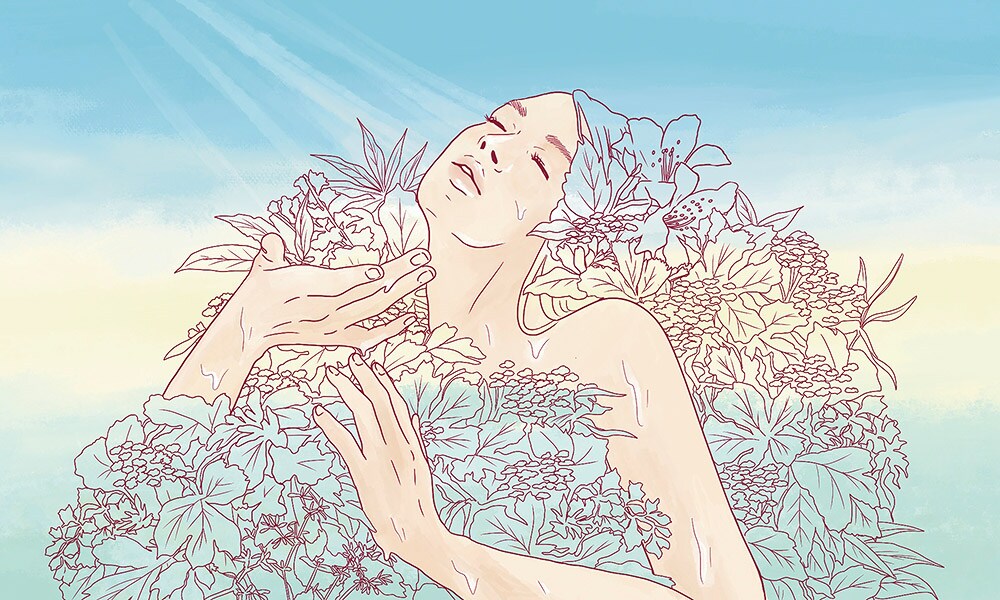
『私の、美しい皮膚』Vol.2
肉厚なシダの葉が重なり合う森の中を、黙々と進んでいる。
見上げれば、ブナの樹冠が滴る緑をくゆらせ、天の高さを知らしめていた。シャワーを浴びながら歩いているような湿気と、隙間のない蝉しぐれが体にまとわりつき、思考を鈍くさせる。
なかなか進まない私の数メートル先を、大きな荷物を背負いながらガイドが歩んでいた。
「霧島ヨウです……宜しくお願いします」
初めて会った時――つい数時間前のことだが――ヨウはその大きな体躯をぎこちなく曲げて挨拶した。客商売とは思えない愛想のなさと、人を跳ね除けるような雰囲気に私はたじろいだ。精悍な顔つきに短く刈り上げた髪、筋骨隆々のからだと日に焼けた肌。それ以外に、ガイドらしい特徴はまるでない。これまで母と旅した時に頼んだガイドは皆ニコニコとして愛想が良かった。依頼を取り消そうかと思ったが、クバル岳の最難関コースを案内できるのはこの人以外にいないよ、と観光案内所の人には説明された。
ツキです、と名乗った私を、じろ、と品定めするような目で見たきり、ヨウは顔を上げない。無言のままどんどん先へ進んでゆく。こいつ、本当にガイドなのか。文句を言いたい気もしたが、延々と続く急斜面に体力と気力を奪われ、口を閉じた。私は動植物に関する詳しい解説が欲しいわけではない。私の目的は、母にかつて愛した土地を体感させることなのだ。
ぬるぬるとした苔が覆う岩道を、滑りそうになりながら這うように登ってゆく。スーツの厚さを調整し、生い茂る植物や虫から肌を守っているにもかかわらず、草木が刺さるちくちくとした感触を錯覚し、いらいらする。パワードユニットを付けて来ればよかった。これぐらい自分の足でも登れるだろうと甘く見ていた。ヨウはパワードユニットなしでも、軽々と岩を乗り越えてゆく。すっきりと刈り上げたうなじから、大粒の汗が滴り落ち、木々の隙間から差し込む光に弾けた。どれぐらい長くこの仕事をしているのだろう。
休憩ポイントに着いた。ヨウは担いでいたクーラーボックスから経口補水液を取り出し、私に向かって差し出す。一気に喉に流し込む。食道を伝いおちる冷たい一筋一筋が、乾き切った全身の細胞全てに沁み渡るようだ。
「お母さんは」
突然、ヨウが口を開いたので私はびっくりした。
「お母さんは、ここへ来れて喜んでんの」
「え、あ、はい、まぁ……多分」
私は首筋のタトゥー型センサに触れた。網膜投影型のレンズ・デバイスをオンにする。視界に、ゆるやかに波打つ青色の模様が浮かんだ。母の脳神経のニューログラフィーは随時私に転送され、母のおおよその感情は知ることができた。
今の母は、穏やかだ。
ヨウは訝しげな顔でふぅん、と言った。こちらに興味があるのかないのかわからない。
「お母さんが、ここに住んでいたのはいつのことなんだ」
「もう40年も前です。戦争が始まる前」
「名前は」
「ウミ」
「……ふぅん」
ヨウの相槌には、歯に何かが挟まったような感触があった。
「年老いてから、急に母はこの島の話をするようになりました。海に潜るのが大好きだったこと、山頂から見る海景色が大好きだったこと。――でも、一度だって来たいとは言わなかった。あれだけ旅行が大好きだった母が、です。もちろん戦争のせいもある。でも、入島できるようになって長いこと経つのに、一度も。その理由を知りたくて、来たってのもあるんです」
ヨウは睨めるような目つきで私を見た。
「あんたの自己満足じゃないの」
腹が立った。なんでそんなこと、こいつに言われなきゃならないのだろう。
「自己満足で、悪いですか」
「悪くない。……ただ、がっかりするくらいなら知らない方がいいこともある」
ヨウの眉間に険しい皺が刻まれた。
「このへんの島らはな、周りの大きな国が力を失ったことや、各国の軍事行動の舞台が宇宙に移行したことで軍事拠点としての価値が薄れて、ようやく解放されたんだ。けど、それで元に戻るわけじゃない。失ったものは帰ってこない。海も山も、まるで別物だ。ルリカケスも消えたし、珊瑚は白化した。町も人も消えた。地形も崩れた。かつて住んでいた土地が変わり果てたのを見て、喜ぶやつはいない」
私にとっては、今の海も山も十分美しい。そう言いかけたが、やめた。ヨウがこの島を愛していることが伝わったからだ。けど、思い出の地がどんなに変わったからといって、そう容易に嫌いになったりするだろうか。その地にこびりついた思い出は、消えないんじゃないのか。
「それでも私は、母が愛したこの地に来てみたかったんです」
ヨウは不機嫌な顔つきのまま押し黙っている。言わなきゃよかった、と私は後悔した。さっき会ったばかりの人間に、私の気持ちなんて、到底分かりっこない。
「あの、セイガ浜の沖のポイントに潜りたいんですが、案内してもらえますか」
仕方がないので話題を変えた。セイガ浜沖はこの島の中でも上級者向けのダイビングスポットだ。
「あのエリアは地形が変わって危ない。あんたみたいな素人じゃ無理だ」
「パワードユニットの出力を最大にしてもですか」
「流れに巻き込まれたら、高確率で死ぬ。熟練のダイバー以外は潜らせない」
「母はよく、あのポイントで潜ってたって言ってました。あそこの海が、この島で一番美しいんだって。母の思い出の場所に潜りたいんです」
「死にたくなけりゃ、黙っていうことを聞け」
横柄な口調に私は苛立った。この人に何を言っても、何を聞いても無駄だ。早く、頂上まで登って景色を見て帰ろう。
やがて、頂上にたどり着いた。母の話では、山頂からの眺めは集落の赤い屋根屋根がコバルトブルーの海に映えてとても美しいとのことだったが、目に飛び込んできたのは、眼下に延々と広がる瓦礫と、打ち捨てられた基地の残骸だった。40年間の歳月が、島を疲弊させた戦禍の跡が、海の美しさをかき消していた。
私たちは無言のまま、岳を降りた。
* * *
海は濃紺に白濁の混じる複雑な表情で、激しいうねりを見せている。
ヴィークルを停めると、ざばんと海に飛び込んだ。センサリースーツのおかげで寒さはないが、それでも衝撃で心臓が跳ねる。こめかみに、きんと差し込むような痛みが走る。
深度を増すごとに視界が暗くなる。10m。20m。海底はもう間近だ。呼吸にまだ余裕があった。流れは強いものの、ヨウが言うような厳しさはなかった。もうすぐ底に手が届く、ふと気を抜いた瞬間、ぐい、と強い力で体が攫われた。海流に捕まったのだ。いくら蹴り上げても、巨人の手で捕らえられたように身動きできない。それどころか少しずつ流されてゆく。焦りが上下を分からなくさせた。海流にきりもみされ、体勢すら整えられないまま、どんどん元いた場所から離れてゆく。肺の痛みが、喉の苦しさが限界を超え、思わず息を吐いてしまった。目の前で泡が散り、気道に海水が流れ込む。もう駄目だ。
意識が遠のきそうになった瞬間、突然、強い力で腕を掴まれた。続いて口に何か硬いものをねじ込まれる。ヨウだった。「吸え」くぐもった声が聞こえ、言われるがままに思い切り息を吸った。塩辛い海水が鼻腔まで入り込み、目の奥がツンと痺れた。頭の中が真っ白になる。一拍おいて、流れ込んで来たのは新鮮な酸素だった。ヨウは私をはがいじめにしたまま浮上した。私とは比べ物にならない力強さで。白い光の帯を抜けた、と思った瞬間、海面に浮かんでいた。
「ばか」
怒声が耳をつんざいた。
「だから言っただろう。泳ぎ方を知らないやつがこんなところで潜るな」
ヨウは私をぐいぐいと引っ張り、自分のボートまで連れて行った。押し込むように乗せられる。浮力から解放された体は鉛のように床に張り付いた。動けない。
「命を捨てにきたのか。誰のための命なんだ」
目の前に、怒りに満ちたヨウの顔がある。床に仰向けに寝た私の体を、覆うように四つ這いになっている。
「いくら人間じゃなくても、波に飲まれたら死ぬんだぞ」
言葉にならない声が、半開きにした口から漏れた。なぜ、分かったのだろう。私は呆然とヨウの顔を見つめた。次の瞬間、強い力で抱きすくめられた。呼吸ができない程の、強い力で。
「頼むから、二度も同じ思いをさせないでくれ」
悲痛な声だった。海水で冷えた体に、ヨウの体温が染み込んでくる。頭の中の、どこかで何かが反応した。背に回された大きな掌。そっと頰に触れる指先。押し当てられた頬の滑らかさ。全てが大好きだった――
こんな記憶は、昨日までは “なかった” 。
私は思わず体を離し、言った。
「あなたは私のお母さんね」
いっときの静けさが、私たちの間を分かち、そして綴じた。

相手は身をこわばらせ、目を見開いている。次に、低く唸った。唸りながら、次の言葉を探しているようだった。私を傷つけまいと、あるいは、自分自身の傷を引っ掻くまいと。
「なぜ分かった」
やがてヨウは言った。
「分からない」
私は答えた。
「なぜ分かったのかが分からない。バグとしか言いようがない」
「……君の、と言うのには抵抗があるが」
ヨウは声を絞り出すようにして言った。
「そうだ。君の元になったツキの、生物学上の母だ。――ウミの元恋人で、元妻だ」
つま、と私はつぶやいた。ヨウはかぶりをふった。
「ああ、そんな古い言葉はもう君たちの世代では使わないよな。パートナーシップに関して、雌雄を特定する名称が使われていた頃の、婚姻制度がなんらかの役割で相手を縛るものだと勘違いされていた頃の」
「あなたがウミの元パートナーで、私の、もう一人のお母さん」
「違う」
ヨウは叫んだ。ついさっき、自分で言ったことを打ち消すように。
「違う。君の母ではない。ツキは一人だけだ。私にとってのツキは……5歳でこの世から消えたんだ。君はツキじゃない。別の人間だ」
「私はお母さんからツキと呼ばれて育った。だから私が」
そう叫んでから、訂正が必要だと思い言い直した。
「私も、ツキです」
ヨウは黙った。
「私はあなたの知っているツキじゃない。でも、お母さんは私を実の娘として作りました。私はお母さんに作られて嬉しかった。私たちは、親子です」
私は続けた。
「ずっと気になっていました。私のもう一人のお母さんは誰なんだろうって。母の相手が女性だと言うことは、なんとなく、感じ取っていました。写真を見た時も、ああ、やっぱりって」
「ウミから詳しく聞いたことは?」
「ない。母は私が5歳になるまでのことについては一度も話したことがない。私の人格の元になった”ツキ” が生まれてから死ぬまでのことは」
ヨウの顔が歪んだ。私はこの人を傷つけている、と思った。優しいヨウ。私には子供もいない。恋人もいない。母しかいない。だからこの人の苦しみは分からない。でも、ヨウと母を見ていると分かる。細胞を新しくし、血液を入れ替え、どれだけ肉体を若返らせても、人間は過去の因縁から逃れられない。どれだけ取り繕っても、一度起きたことはその人の体の中に残り続ける。ひと目だけ編み間違えたセーターの穴が、着るたびにざらざらと指に引っかかるように。
でも、私は、この傷ついた老人――写真の中で、ヨウと母はほぼ同年代に見えた――から、全てを聞かないと行けないのだ。
「君がツキから作られたと言うことはひと目でわかったよ」ヨウは言った。
「君の顔は、私が昔に思い描いていた、成長したツキの姿に瓜二つだ」
「母は死んだツキが成長して20歳になった時の頃をイメージして私の外見(フォルム)を作ったと言っていた。あなたも、お母さんも、頭の中で同じ姿を描いていたってこと」
「最後まで、何も話さないつもりだった。気づかれないまま、さっさと帰ってもらおうと。今日だって、放っておくつもりだった。でも、思い直した。君がツキの人格をベースに作られているなら……ウミの性格を引き継いでいるなら、きっと私が止めても、言うことなんて聞かずに潜りに行くだろう、と」
「今まで分かりませんでした。あまりにも写真とは、見た目が違うので」
「外見を変えたくなるような出来事がたくさんあったんだ。特に、戦争の間は」
ヨウは短く言った。その言葉に、ヨウの人生における、「ツキの母」としてではなく過ごした膨大な時間の重なりを私は初めて感じ取った。
「自覚はしていなかったが、これが私の長いこと望んでいた本来の姿なのだろう。時代が変わって、技術が進歩して、今やっとそう感じられるよ。超国家企業に依存している今の状態は好ましくはないが、技術を提供してくれたことには感謝してる……ただ、」
ヨウは顔をあげた。その顔は、変わらず苦しげに歪んでいた。
「何でもかんでも、受け入れるわけには行かない。どの技術を受け入れるかは、それぞれが、それぞれの中で線引きをしなけりゃいけない。私は君を、ツキだとは思えない。例え人格のベースがツキにあったとしても、細胞の元をツキから取っているとしても、君は、あのツキじゃない。ツキは死んだんだ。5歳の時、ウミが目を離した隙に家から出て海に入り、高波に攫われて」
「母を責めた?」
「責めるわけがない。あんなに傷ついて自分を責めている人間を。私はウミを愛していた。その事件のせいで、ウミを愛さなくなったわけでもない」
ヨウの瞳の表面に、光が揺れる。感情の揺らぎがそうさせているのか、瞳に映る波のせいなのか、分からない。
「救急医療のおかげで、娘は一命を取り留めた。けど、植物状態になった。一年もの間、ツキはよく頑張ったよ。けど、駄目だった。私たちは彼女に何もしてあげられなかった。一度も意識を取り戻さないまま、6歳になる直前に彼女は亡くなった。私はウミに、もう一度子供を作ろうと言った。彼女は拒否した。それも仕方がないと思った。彼女の中で、ツキと過ごした5年間の記憶は絶対だった。もしまた子供ができたとしても、ツキの記憶を重ねてしまうだろう。彼女はそれは、次の子にとっては不幸なことだと思ったんだろう。そう思って納得していたのに、ウミは、」ヨウは顔を歪めた。
「ツキが死んで5年が経って、私に黙ってツキのクローンを作ろうとしたんだ」
(Vol.3へ続く)
-

- 小野美由紀(おの・みゆき) 1985年生まれ。2015年にデビューエッセイ集『傷口から人生。メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった』(幻冬舎)を刊行。ほかに、絵本『ひかりのりゅう』(絵本塾出版)、旅行エッセイ『人生に疲れたらスペイン巡礼〜飲み、食べ、歩く800キロの旅』(光文社新書)、小説『メゾン刻の湯』(ポプラ社)、『ピュア』(早川書房)がある。企業と協業してSF小説を執筆するSFプロトタイピングでも幅広く活動中。
デザイン/WATARIGRAPHIC