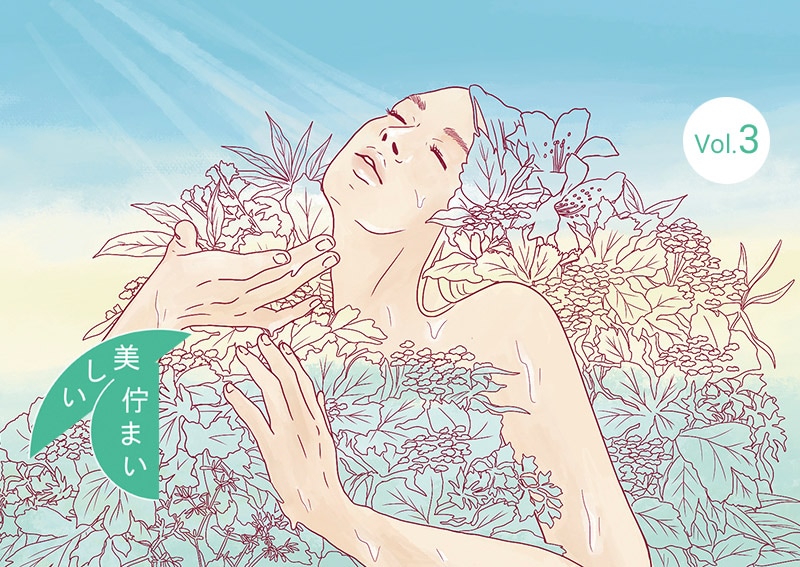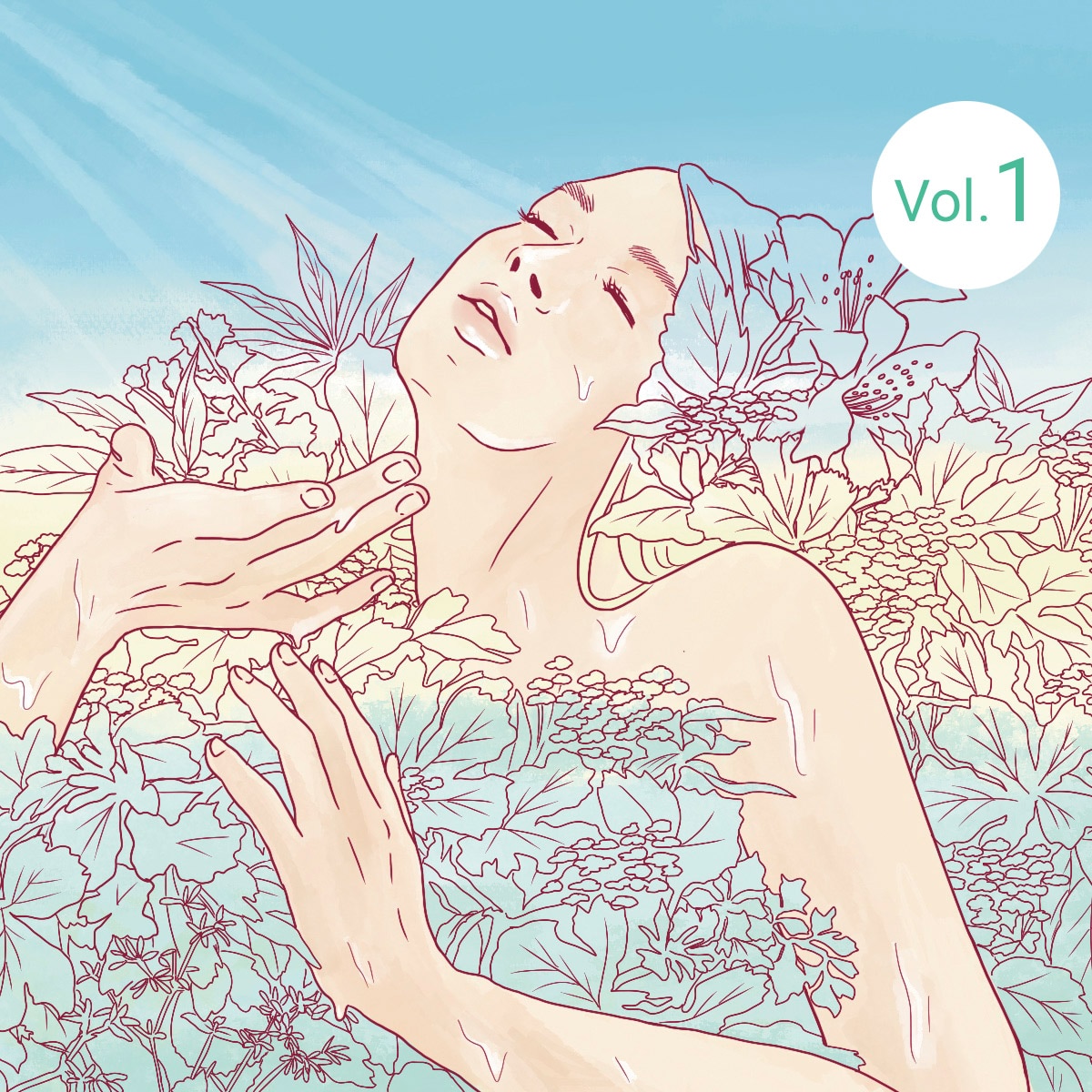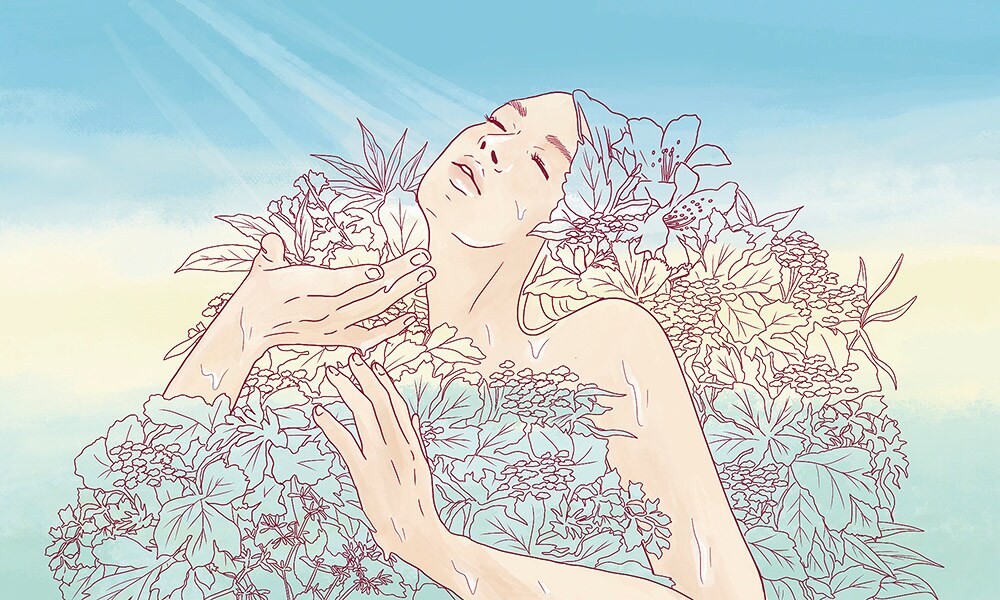
『私の、美しい皮膚』Vol.3
「ツキが生きている間に、母はツキの細胞を保存していた?」
「そうだ。私はそれだけは許せなかった。あの頃は人間のクローンを認証するかどうかで世界中がまふたつに割れていた。あの頃、私は再三、こうした技術は受け入れられない、生き物として間違っているとウミに話していた。ウミは、きっと私に相談すれば反対されると思ったんだろう。勝手にウミのDNAを保存していて、承認が下りるのを待って、クローンを作ろうとした。ウミの実家は裕福だったから、それぐらいはお手のものだった。冗談じゃないと思った。私だってツキの親なんだ。どちらか一方がより母親だという意識を持たなくていいように、人工子宮での出産を決めたのに」
「卵子同士の生殖は間違ってない?」
「私もそれについては迷った。迷ったよ。でも踏み切った。私たちは子供が欲しかった。ウミを愛してた。世間でどう言われようと、ウミとの子供だったら、きっと3人で幸せに暮らして行けると」
ヨウの顔に、かつての愛の面影が見えた。塩混じりの砂がパラパラと肌に刺さる。私の皮膚ではなく、センサリースーツに。ひりつく不快さが噛み付いてくる。私はそれを払わずに、ヨウの言葉をじっと待った。ヨウは過去の記憶に没入している。
「最初にウミにあった時のことは、今でも覚えているよ。彼女は最初、観光客としてこの島に来た。ウミって名前なのにウミのない県で生まれたの、と言って笑ってた。彼女の泊まっているホテルのオーナーから、スキンダイビングをやりたい客がいるからガイドを頼めないかといわれて出会ったんだ。小さな島で、まだ戦争も始まっていなくて、若い人間も少なく、孤独だった。法律で同性婚が認められたとニュースで流れてきたが、この島には関係ないだろうと思っていた。一生この寂しさを抱えて一人で生きるだろうと思っていた。でも、彼女に出会って、それはただの思い込みだと気付かされた」
「彼女は飲み込みも早くて、新しいことをやりたがりで、いち早く上級者向けのポイントで潜りたがるから止めるのが大変だった。2ヶ月に一回の島通いが1ヶ月に一度になり、そのうち、京都のマンションを引き払って私の家に転がり込んだ。島で女同士で結婚したのも、子供を作ったのも私たちが最初だった。今では特段、珍しいことでもなんでもないが」
「彼女は強かった。欲しいものを欲しいという強さがあった。それが、ツキが死んだ後で、弱さに変わったんだ」
ヨウの顔に濃い影がかかった。私は振り返った。空を塗り込めるような巨大な雲が、私たちの頭上に迫っていた。
「私たちの間には埋まらない溝ができた。ウミは、あなたは私を幸せにすると言ったよね、と何度も言い、私を責めた。確かに、結婚した時に私はそう言った。子を亡くした人間の悲しみから来る言葉だと、受け止めるには私も打ちのめされすぎていた。抱えきれない無力感が、私たちの生活を支配して、色褪せさせて行った。そのうち、追い討ちをかけるようにあれが起きた」
「戦争、」
「そうだ。本土出身者はみな逃げ帰ったよ。ウミは、誰より先に逃げた。つまらない場所だ、といつも言っていた故郷にね。『もう二度とこの島には来ない』と言い残して。私はそれが正しい選択だと思った。辛い記憶の残る場所に、いつまでも居続ける必要はない」
「あなたは逃げなかったの」
「私は、残ると決めた。ここが私の土地だから。ツキが眠るこの場所から離れたくなかった。……その選択は、今も間違ってなかったと思うんだ」
ヨウは姿勢を直し、私に向き合うと、
「もう二度と、話すことはないと思っていたよ……なあ。ウミ」
私の向こうにいる人間を探して声をかけた。
「ウミ、そこにいるだろう。ヒューマノイドとして再生したツキの体を借りて、ここへ来たんだろう」
「母は返事ができません」
私は言った。
「母には意識がありません。数年前から認知症を患い、今では病気が進行して植物状態になりました。話しかけても返事ができません」
ヨウは息を飲んだ。
「私がここに来たのは、私の意思です」
私は言った。
「私の海馬には、ヒューマノイドの製造会社が母の記憶から吸い上げた“ツキ”に関する膨大なデータが保存されています。母によって再現された私のデジタル人格には、5歳までの記憶は残されていません。吸い上げたデータのうち、何をヒューマノイド本人の意識上に残すかは、オーナーの手によって決められます。母は5歳までのツキについて、いっさい私に知らせなかった。語ろうともしなかった。もちろん、あなたについても」
彼は黙り込んだ。私は続けた。
「私の人生は幸せでした。母は私を愛してくれました。私たちはずっと一緒でした。母が元気なうちは、一緒にあちこち旅をしたし、母が老いて、体が不自由になってからは、旅行好きだった母の代わりに私が母の皮膚をまとって旅をしました。私たちは同じものを感じ、同じ体験をしました。私は母が好きだし、母の望むことならなんでも叶えてあげたいと思った」
「認知症が進行してから、母は過去の記憶を楽しそうに語り始めました。驚きました。母は陽気な人でしたが、過去のことを語るときにはどこか辛そうでした。私は母の過去について、知りたいと思い始めました。けど、母の語りにもまた、まだらに抜け落ちている部分があるように思えました……それが、病気の進行によってなのか、それとも残っている母の自我が意図的にそうしているのか分かりませんでした。けど、私にはそこが大事だと感じました。母が頑なに抗老化を避け、病気をそのまま受け入れる理由と、繋がっているように思えたのです」
「認知症は、今では治療可能なはずだろう。神経細胞の再生薬と培養脳細胞の置換手術は随分前に一般化したし」
「そこなんです」
私は言いたくないことを言わざるを得なかった。
「法的な書類によって、母は一切の治療や延命措置を拒む意志を残していたんです」
「私には理解できませんでした。母の病気が進行するにつれ、疑問はどんどん大きくなりました。老いのない体を誰もが手に入れたがっている中で、なぜ母はそうしないのだろう。母に治療を拒ませるものは何なのだろう、と。狼狽え、必死に何か、母を説得する方法がないか探しました。でも、無理でした。母は意思疎通アプリを使用しての会話すらも拒んでいたから、取り付く島もなかった」
波が岩壁にぶつかる轟音が、私たちの間に響く。
「ただ、植物状態でも、触れたり、呼びかければ反応はするんです。私があちこちセンサリースーツを着用して旅したのは、とりわけ若い頃に体験していた皮膚刺激に対して彼女がポジティブな反応を示すからです。……意識がない母に、かつて暮らした場所の空気を、味わわせてあげたかった」
「それで、ここに?」
「……」私は首を振った。
「違う。本当は、知りたかった。だってもし、母が死んだツキへの償いのつもりで、延命を拒んでいるんだとしたら」
喉が締め上げられるようで、呼吸が苦しい。鼓動が溺れかけた時よりもずっと速く胸を打つ。
「私の存在意義は、結局は母にとってなかったってことじゃないか」
私は座り込んだ。海水に濡れた肌に、より塩辛いものが伝ってゆく。
ヨウは何も言わない。何も言えないだろう。黙って私を見下ろしている。しばらくそうしていたが、背を向けるとボートを操縦して岸に向かい始めた。エンジンの音が二人の間を隔てた。岸に着く頃には涙も海水も乾いていた。
岸につき、ヨウは私をボートから下ろすと車に乗るよう促した。
車の中で私たちは無言だった。砂利道の激しい隆起が、波に揉まれて疲れた体を苛んだ。ヨウはずっと、何かを言いたげだった。逡巡する気配が、小さな車内に充満する。
「なぜ、私があなたがもう一人の母だと気づいたか、ですが」
私が口火を切った。
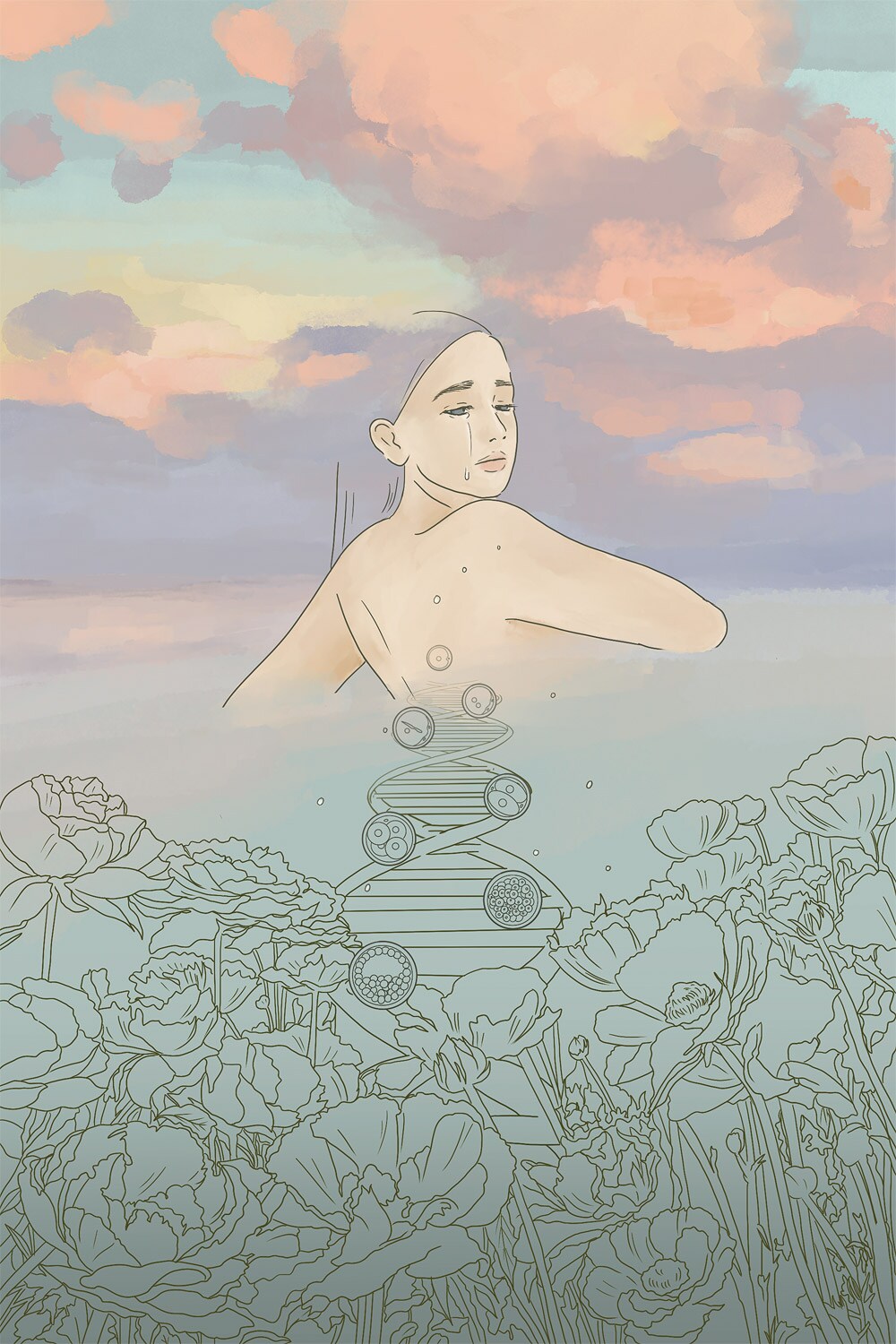
「多分、このスーツが原因です」
ヨウは怪訝な顔をしている。
「あなたの肌に触れたことで、入力された皮膚刺激から、私があなたに抱かれていた小さな頃の記憶を、ツキの人格AIが捏造したということです。……母の記憶から吸い上げられ、私のキャッシュから消された、ツキの人格の残り香のようなものが」
「よくわからないけど、お前の中のツキがそれを思い出したということか」
「はい。これはバグです。そうとしか言いようがない。なぜそんな間違いが起きたのか、私にはわかりません。けど、分かるのは、それがほんとうに起きたからこそ、その記憶が “生まれた” ということです」
記憶というものは不思議だ。思い出すまで、そこには存在しない。思い出して初めて「そこにあった」ということに我々は気づく。まるで手品師が虚空から鳩やウサギを取り出すように、トリガーがあって初めて、それを記憶していたという事実がわかる。それまでは、無だ。私たちは、それがそこにあることがわからない。
「そんなことが……」
ヨウは驚いた様子だったが、しばらくして、ポツリと言った。
「私は古い人間だからね、君の母親にはなれない。娘を救えなかった人間が、そう名乗る資格はない」
「そうでしょうね」私は言った。すっかり気持ちは沈んでいた。
「明日、帰ります。あなたに辛い思いをさせたくありません。私が来たのは、間違いだった」
しばらくして、ヨウは車を止めた。山の麓に、樹木に覆われるようにして、古びた一軒家が建っていた。
「ここが私の家だ。……ホテルに戻るには、もう遅すぎる。この坂の下に、ゲストを泊まらせるためのコテージがある。今日はそこに泊まりなさい」
「一つ、聞いて良いですか」私は言った。
「なぜ、あなたは老いを拒み、若い肉体を手に入れたのですか。辛い思いをしながら、なぜ長い人生を求めるのですか」
ヨウは、程なくして口を開いた。
「この数十年間で、私たちはあまりにも多くのものを失った。生まれた場所が壊れるのは、半身が引きちぎられるように辛かった。辛かったが、終わった。この島はようやく自治権を得た。……もちろん、自治とは名ばかりだが、顔も見たこともない奴らに暴力で好き勝手にされるよりは、まだましだ。好きにするんだ、これからは。死ぬまで、あと40年か50年はある。ずっとここで暮らして、この島のために、できることをするさ。この人生を、生きるに値するものにするために生きるんだ」
「パートナーはいる?」
「いない。ウミのことは、恨んでもいるが愛してもいる。愛の記憶があるうちは、人は過去にはならない」
* * *
その晩、坂の上の家から、木々のざわめきに紛れて1匹の獣のような慟哭が響いてきた。耳に入れるべきかわからなかったが、波に攫われて疲れ切った私の体は重くだるく、鉛のように布団に沈み込み、四肢を無碍に放り出したまま、横たわっていた。母にもきっと届いていたはずだ。通信はオンにしたままだった。母のニューログラフは穏やかだった。何も感じていないのかもしれないし、何かを感じているのかもしれなかった。
なぜ、私には彼女のことがわからないのだろう。
* * *
ポートの周りにはまばらに人が散り、別れを惜しんだり、写真を撮ったりしている。遠くに停まるフェリーは大きな船体を、海に反射した光の中で輝かせている。
桟橋の前に、ヨウが立っていた。見送りに来るとは思わなかった。明け方、コテージを抜け出して集落へと戻り、荷物をまとめて昼の便に間に合うようにここに来たのだ。
「この便で帰るかと」
ヨウの顔はやつれていた。目の下がくすんでいる。今もセンサリースーツを着ているのか、とヨウは聞いた。私はうなずいた。
本当は飛行機で帰るつもりだった。やめたのは、もう少しだけ、母の愛したこの島を味わって帰ろう、と思ったからだ。肌に受ける潮風を、皮膚を焦がす太陽の匂いを、網膜に刻み込まれる、深くて重くて、底なしで、強烈で、静かなエメラルド・グリーンを。
「一つ、聞いていいか」
ヨウは言った。
「ウミが死んだら……君はその後はどうするんだ」
「わかりません」私は答えた。
「私は母の介護用ヒューマノイドとして作られました。母が死んだあと、自分がどうするべきかは何もわかりません。ただ、」
私はヨウの目を見据えた。
「あなたは認めなくても……私たちは人間です。去年、私たちの人権を認める法令が施行されました。人間と同じで、仕事を選び、伴侶を得て、自分の人生を生きる権利があります。だから、私もきっとそうするでしょう。自分の人生を生きることになる」
苛烈な少子化による人口減少、それに伴う労働力不足を補うため、私たちは社会に普及した。これからは人間と対等の存在として、社会の中で権利を持つだろう。私は自分の人生をこれから選び取らなければならない。母がこの島に自らの意志で来たように。ヨウが島と共に生きることを選んだように。それがどういうことなのか、私にはまだ、想像がつかない。
そうか、とヨウは言った。
今度は私が問う番だった。
「あの、お願いがあるんです」私はヨウに言った。
「もう一度私を抱きしめてくれませんか」
「ウミのためか」
ヨウは聞いた。私は頷く。
「母は、多分、まだあなたのことを愛していると思う。それぐらいは、私にも分ります」
ヨウは私の体に腕を回した。長い、体温の高い腕が私を締め付ける。汗の滲んだTシャツが頬に張り付いた。私ではない、そこにない体を抱きしめている。
しばらくそうしていたが、やがてヨウは体を離した。
「スーツを脱ぎなさい、ツキ」
ヨウは言った。森厳な、けれども包み込むような声で。母以外から命じられたのは初めてだ。
私はスーツを脱いだ。私の本当の肌が顕になる。見た目には何も変わらない。今までと変わらないはずなのに、1枚分だけ、感覚が強くなった気がした。素肌が潮風に触れる。培養細胞で作られた、人の皮膚と同じ機能を持つ、私の肌が。
ヨウの手が私に触れる。分厚い、凹凸のある手のひらが私の頭を撫でる。私の頭は髪の毛に覆われている。彼の手のひらの深い畝が、私の髪の毛の一本一本をとらえる。髪に神経はないはずなのに、この人の手の表情がわかるのはなぜだろう。
「よく帰ってきた」
私は目を見開いた。
ヨウは私を見ている。私の虹彩がヨウの視線を感知する。人間が視線を熱いとか、冷たい、とかいうのはなぜだろう。本当はそこには何もないはずなのに。
「こう呼ぶことにまだ、ためらいがある。君をツキと認めることはできない。君は君だ。あの小さなツキじゃない。でもウミにとって、君は大切なツキだし、君が彼女を大事に思っているのはわかった。それで十分だ。ありがとう」
ヨウはもう一度私を抱きしめた。手のひらが私の背を包み込む。張り詰めていた身体中を走る神経繊維の一本一本が、許されたようにほどけてゆく。
「自分がこう感じているのが不思議だ」
ヨウの声が耳元で聞こえる。声は耳殻の中の産毛をそよがせ、温かい液体のように私の中のどこかの器に注がれる。
「最初は偽物だと思っていた。でも、嬉しい。……君が来てくれて、とても、私は嬉しい」
ヨウは泣いていた。私は泣けない。私に涙の機能はない。代わりにヨウの涙を見つめる。涙の粒の中に光る海があるのを見つける。私たちはもう一度互いの目を見つめ合い、互いの肌を抱きしめ合う。
(3回連載終わり)
-

- 小野美由紀(おの・みゆき) 1985年生まれ。2015年にデビューエッセイ集『傷口から人生。メンヘラが就活して失敗したら生きるのが面白くなった』(幻冬舎)を刊行。ほかに、絵本『ひかりのりゅう』(絵本塾出版)、旅行エッセイ『人生に疲れたらスペイン巡礼〜飲み、食べ、歩く800キロの旅』(光文社新書)、小説『メゾン刻の湯』(ポプラ社)、『ピュア』(早川書房)がある。企業と協業してSF小説を執筆するSFプロトタイピングでも幅広く活動中。
デザイン/WATARIGRAPHIC