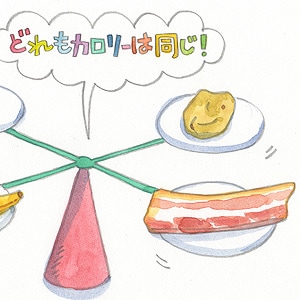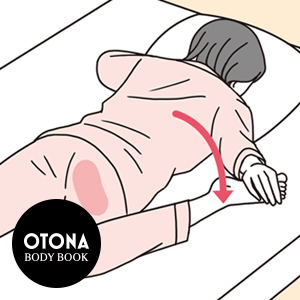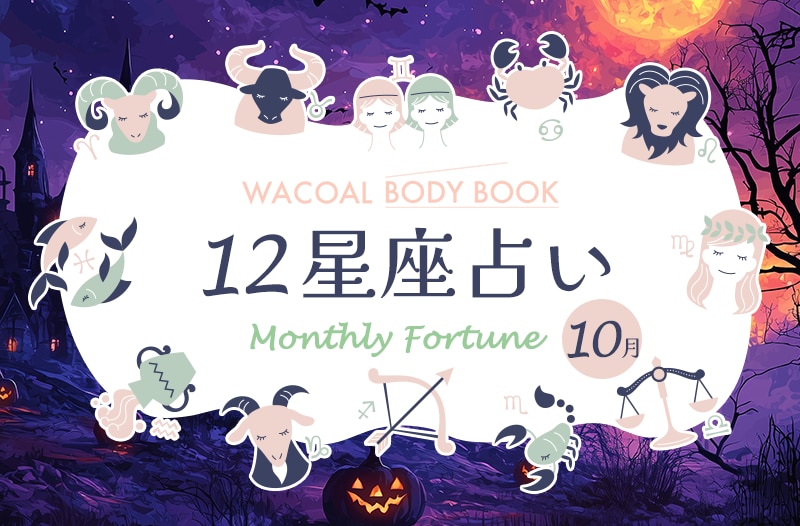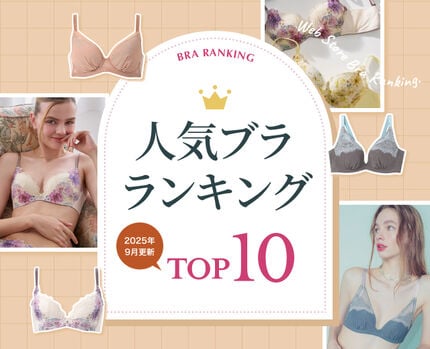- 新訳からだ辞典「パンツ一丁」
- 2019.01.30
今月のコトバ「腰(コシ)がある」

カラダも麺もコシが大切!
腰(コシ)とは、人体の骨盤のある辺りで、屈伸をつかさどる大切な部分である。では「腰がある」という表現はどうだろう。「餅・うどん・そばなどの歯ざわりがしっかりしていてねばりがあること」あるいは「布・紙などの手ざわりがしなやかで丈夫であること」。つまり、カラダにおける腰のように、内側から支える強さを表すポジティブなコトバなのだ。「芯」は単に内側のかたい部分のことだが、「腰」には弾力感がある。理想的なのは適度な腰のある「しこしこ」「ぷりぷり」「もちもち」の食感ではないかと思うが、芯と腰の境目はどこにあるのだろうか。博多ラーメンには「バリヤワ」「ヤワ」「普通」「カタ」「バリカタ」「ハリガネ」「粉落とし」「湯気通し」というような茹で加減の段階あるが、「普通」または「カタ」くらいが適度な腰なのかなと個人的には想像する。
というか、それ以外はこわくて注文できない。福岡出身の友人はいつもバリカタを頼むし、イタリア人の友人は「粉落としサイコー」と言うが、私としては、おそるおそる「カタ」を頼みつつ、バリカタやハリガネの腰に思いをはせるのが関の山だ(粉落としや湯気通しの存在は無視)。しかし、やわらかさのバリエーションが乏しいのはなぜだろう。バランス的には「ふにゃふにゃ」「くたくた」「とろとろ」があってもいい気がするが、麺はやっぱり腰が命なのだろう。
やわらかさは幸せである
とはいえ、麺の世界を除けば、人気があるのは圧倒的にやわらかさのほうである。カラダはやわらかいほうがいいとされ、頭だってやわらかいほうが愛される時代。フワフワのパンケーキやとろとろのオムレツは、温かい幸せ感と直結し、私たちを腑抜けにさせてしまうのだ。コピーライターの仕事をしていると「かたい文章をやわらかくして」と依頼されることがよくある。「やわらかい文章をかたく」という依頼もあるけれど、広告の場合は、やわらかめオーダーのほうが圧倒的に多い。文章をやわらかくする場合、漢字や難しい言葉をなるべく避け、ひらがなを多用し、文字量を減らし、さらに書体を大きめにして、目にもやさしい雰囲気にゆであげるわけだ。
しかし、ただ単に文字数の少ない平易な文章にするだけでは、情報量が減り、内容に深みがなくなるばかりで、この深みを腰と言い換えてもいいかもしれない。読みやすくやわらかめにリライトしつつも、適度な読みごたえ、噛みごたえを残そうとコピーライターは今日も苦心するのである。まるで麺職人のように。
コシのある腰巻きを見つけた
というわけで、広告のバリヤワな文章は、活字中毒の人には物足りないのではないかと思う。バリカタ以上の読書体験を求める人におすすめしたいのは、たとえばこんな本だ。昨年末、国書刊行会から発売された分厚い小説『JR』は、2段組みで940ページ。見るからにずっしりと腹もちがよさそうな本で、価格もフルコースディナー並みの8,000円(税抜き)。気持ちとしては「湯気通し」を頼むくらいの勇気と覚悟が必要とされそうだ。JRとはJAPAN RAILWAYの略ではなく、11歳の少年の名前であるらしい。帯には「世界文学史上の超弩級最高傑作にして爆笑必至の金融ブラックコメディ! 殊能将之 熱讃の書 奇跡的邦訳!! 全米図書賞受賞作」など、漢字多めのコピーが踊る。この帯だけでも、相当な噛みごたえである。
本の帯は、別名「腰帯」「腰巻き」ともいい、中身の魅力をアピールする大切な広告部分だ。そういえば本には「背」もあるし、紙を綴じた部分は「喉」という。本のカバーは「ジャケット」だし、カバーを内側に折り曲げた部分は「袖」ではないか。1冊の本は、まさに服をまとったカラダのようで、大切に扱わなければと改めて思う。ページを激しくめくっても破れないのは、もちろん、腰のある紙が使われているおかげである。
相川藍(あいかわ・あい)
言葉家(コトバカ)。ワイン、イタリア、ランジェリー、映画愛好家。
好きなネット用語は「パンくずリスト」。自分が今どこにいるのかを示す階層表示のことだが、ヘンゼルとグレーテルが森で迷子にならないよう通り道にパンくずを置いていったエピソードに由来すると知り、キュンとした。