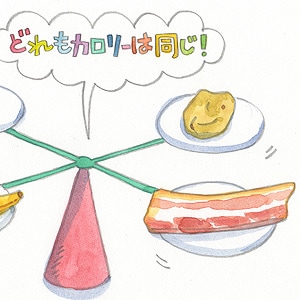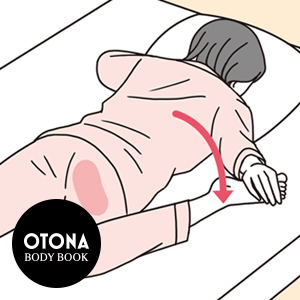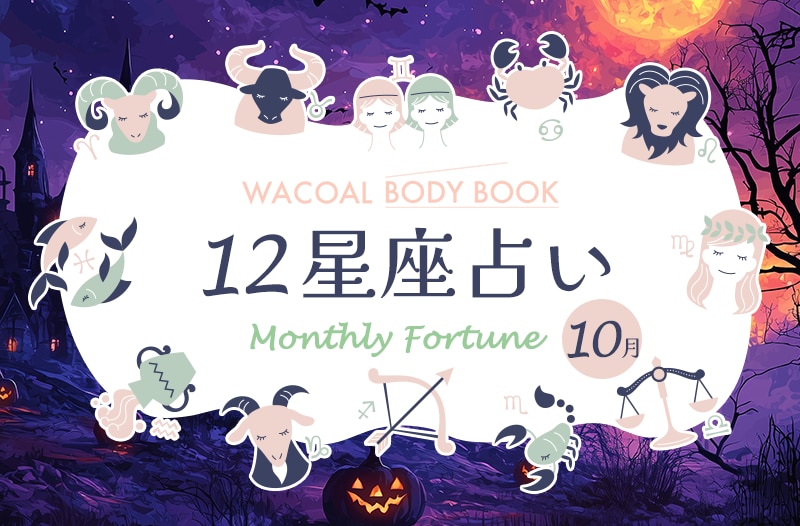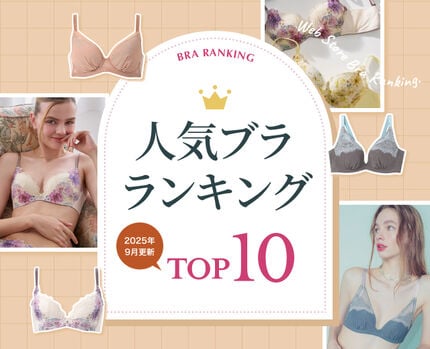- 新訳からだ辞典「パンツ一丁」
- 2016.10.26
今月のコトバ「ガードル」

ガードル VS ゲートル
「ガードル(Girdle)」とは何か。ずいぶんと骨太で重みのある語感だが、大辞泉を引けばその意味は「女性の腹部・腰部を整えるための基礎下着」とそっけない。語源は「ガード(Gird:締める)」+「ル(le:物を表す接尾語)」=「締める物」。「ガード(Guard:守る)」ではないところが、このアイテムのポイントだろう。もともとガードルにはベルトや帯の意味もあり、からだを締めるタイプの下着であることは間違いない。ガードルと似た言葉に、フランス語由来の「ゲートル(Gaiter)」がある。兵士が足のスネにゲートルを巻いている写真を見たが、ズボンのすそが汚れたり、靴に砂が入ることを防ぐための装備であるらしい。長時間歩行におけるうっ血防止の効果もあるようだ。つまりゲートルは、サポーターやスパッツの仲間。ガードルとは「友達の兄貴」くらいの関係といっていいだろう。
その他の似た言葉としては「レードル(Ladle)」があり、これは「お玉」とほぼ同義語。「ニードル(Needle)」は針であり、「ヌードル(Noodle)」は麺で、「プードル(Poodle)」は犬である。「ハードル(Hurdle)」は高く、「シードル(Cidre)」は甘い。そろそろこの辺でやめときます。
コルセットからパンツへ
ガードルの祖先は、中世ヨーロッパで生まれ、19世紀に流行したコルセットである。「まっすぐな背筋・高く突き出したバスト・細いウエスト」という当時の理想的なボディづくりに貢献したコルセットだが、重く動きにくかったため、次第にその機能は上下に分離した。ブラジャーとガードルの形へと進化し、柔らかく伸縮性のある素材でつくられるようになっていったのだ。今やガードルは「きつい・苦しい・かっこ悪い」の3Kイメージとは別次元のアイテムとなった。「ビジリーナ」「ハミデンヌ」「バレリーナfit 」「肌リフト」など、最近の商品はネーミングもお茶目である。ガードルが、こんなにカジュアルで日常的な下着になるなんて、だれが想像しただろう。
ネーミング例はまだまだある。「-5歳の着やせパンツ」「-5歳のくびれパンツ」「薄くて軽いきちんとパンツ」「キャッチアップパンツ」「メリハリヒップパンツ」「おなかシェイプパンツ」「スリムアップパンツ」「ソワレパンツ」「プリンヒップパンツ」......。ガードルはもはや、パンツなのか?
ガードルを脱がせるとどうなるか
ネピアの「モイスチャーティッシュ」という商品が、「鼻セレブ」という名前に変えたことで売り上げが飛躍的に伸び、大ヒット商品になったエピソードをご存じの方も多いだろう。鼻あたりのやさしさと高級感が伝わる優れたネーミングだなと思う。同様に、ソフトな肌あたりを想像させる「肌リフト」というネーミングが、旧来のガードルの締めつけイメージを払拭してくれることは間違いない。そっと、すべるような感触で、ボディラインを引き上げてくれるのではないか。そんな期待が高まるのは、ろくろを回すようにからだに触れるだけで美しいヒップが造形される、この商品のCMを見てしまったからかもしれないけれど。
ガードルについて考えていたら、コピーライターの神様といわれる仲畑貴志さんの仕事を思い出した。「愛という感情を、ロボットに抱くとは思わなかった」というAIBOのコピーが私は好きだが、タマムシのような昆虫の写真に添えられた「服を脱がせると、死んでしまいました」というコピーも忘れられない。1986年のワールドの広告だ。
バブル時代の人間は、服を脱がせると死んでしまったのだろうか? いやいや、図太く生きていたはず。だけど当時はボディコン全盛期。「ガードルを脱がせると、ヤバイ状態になりました」という人は多かったんじゃないだろうか?
相川藍(あいかわ・あい) 言葉家(コトバカ)。ランジェリー、映画愛好家。最近いいなと思ったのは、映画「暗くなるまでこの恋を」で妻(カトリーヌ・ドヌーブ)の裏切りに気づいた夫(ジャン=ポール・ベルモンド)が、彼女の下着を次々と暖炉で燃やすシーン。