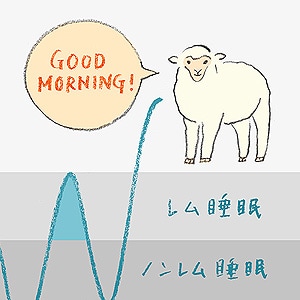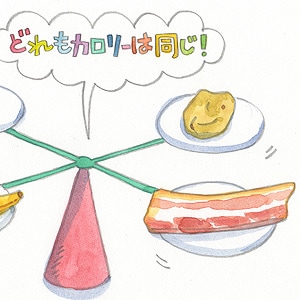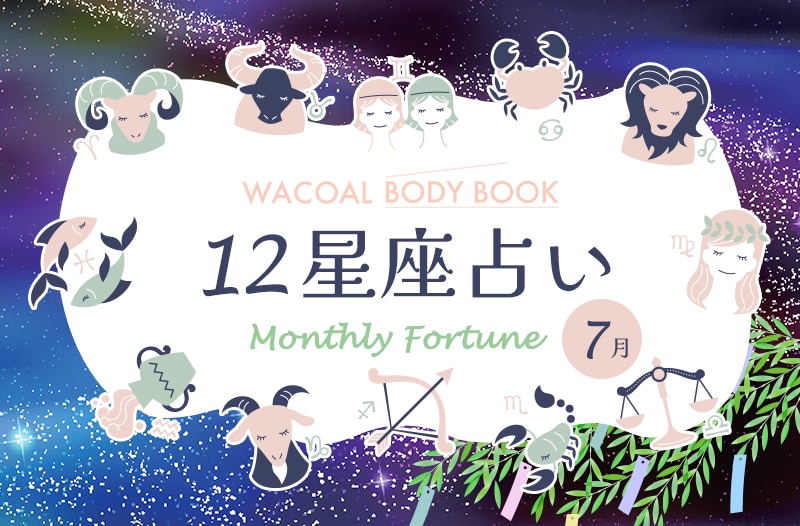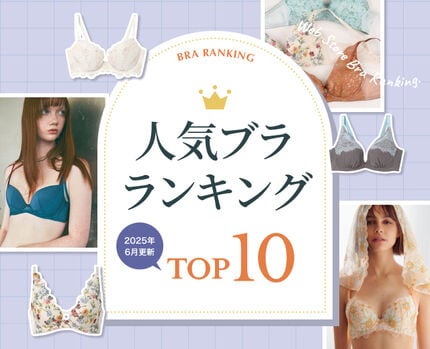着倒すはサステナブル
「着倒す」とは、徹底的に着ること。コーディネイトを考えながら毎日の装いに変化をつけていく軽やかな動詞「着回す」に対し、「着倒す」は、ひとつのアイテムへの偏愛を感じさせるコトバだ。「飽きるまで、こいつを着まくってやるぜ!」という強い集中力と覚悟が感じられる。
「着倒す」は「蹴倒す(けたおす)=足でけって倒す」にも響きが似ているし、なにしろ「倒す」という動詞自体が勝負ワードだから、ちょっとコワイくらいの勢いがある。しかし、動詞の連用形につく形の「〜倒す」は、打ち負かす意味ではなく「とことんやる」という意味。いじり倒す、しゃべり倒す、遊び倒すなどもよく耳にするけれど、勝ち負けは関係なく、行き着くところは自己満足の爽快さにあるような気がする。
服を着倒し、靴を履き倒し、本を読み倒す。これらの表現は一見荒っぽいが、実際の意味としては、タンスの肥やしにせず、愛情を持って繰り返し使い続けることであり、ひとつひとつのものを大切に活用するサステナブルな生き方といえるだろう。最近のファッション誌では、1着の服をセンスよく自分のものにしていくニュアンスを加えた「着こなし倒す」なんていう表現が使われていた。さあ、今年は、どんな服や下着を着こなし倒そうかと考えると、ワクワクしてくるではないか。
着倒れは恋に似ている
「着倒す」と似たコトバに「着倒れ」があるが、こちらは、服にお金をかけ過ぎて財産をなくすこと。つまり極端なことを言えば、「着倒す」でボロボロになるのは服、「着倒れ」でボロボロになるのは人間のほうなのである。ただし現在ではネガティブな意味合いは薄れ、どちらもユーモラスな誇張表現として使われることが多い。
昔から「京の着倒れ、大阪の食い倒れ」といわれるが、これは、京都の人は衣服にお金をかける着道楽で、大阪の人は飲食にお金をかける食道楽の気風があるということ。観光客を惹きつける宣伝コピーのような役割を果たし、その後「神戸の履き倒れ」「江戸の飲み倒れ」などが連鎖的に生じてきたようだ。
衣食住のうちの食や住を削ってでも衣のほうに人生をかけ、ひとつのブランドを追いかけて集めている人たちを撮影した『着倒れ方丈記 HAPPY VICTIMS』(都築響一/青幻舎)という写真集がある。狭い自室でお気に入りの服に囲まれたコレクターたちの姿は幸せそうだが、撮影時から約20年が経過した今見ると、レトロな面白さが加わって一層味わい深い。ある時期に、彼ら彼女たちが着倒れるほど夢中になった服たち。それはどこか恋愛の記憶に似ている。
着たいものを着る!
倒れるという動詞はドラマチックだと思う。坂本竜馬の名言に「倒れるときは前のめり」というのがある。司馬遼太郎が著書『竜馬がゆく』の中で「業なかばで倒れてもよい。そのときは、目標の方角にむかい、その姿勢で倒れよ」「男なら、たとえ、溝の中でも前のめりで死ね」などと竜馬に言わせたのだ。
これらのバリエーションとしては、『太平記』由来の「倒れても土をつかむ(=倒るる所に土を摑む)」や「転んでもただでは起きない」がある。倒れるという失態を反転させる不屈の根性には見習うべきものがある。なんとポジティブで、しぶとくて、ちゃっかりしていることか。
前述の『着倒れ方丈記』には、自他共に認める「日本最大のゴルチェの顧客」という人の、運命の出会いエピソードが紹介されていた。彼女はゴルチェのパンツに一目惚れし、サイズが合わないにも関わらず即購入し、部屋に吊して眺めながら「いつか着てやる」とダイエットに励み、見事8キロ減量。以来、服はすべてゴルチェで通すことにしたのだという。美しい話である。「これを着たい」という強い気持ちは誰にも止められないし、好きなアイテムを着倒すことで得られる喜びは、誰にとっても計り知れないほど大きいだろう。
-
相川藍(あいかわ・あい)
言葉家(コトバカ)。ワイン、イタリア、ランジェリー、映画愛好家。
好きなイタリア語は「スプーニャ(=スポンジ)」。ずぶ濡れになることを「スプーニャになる」といい、浴びるほど酒を飲むことを「スプーニャのように飲む」という。
からだをスポンジにたとえるなんてカワイイ。