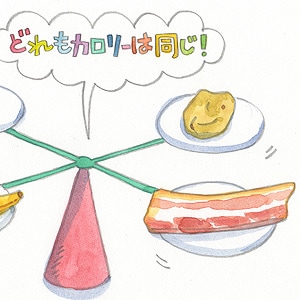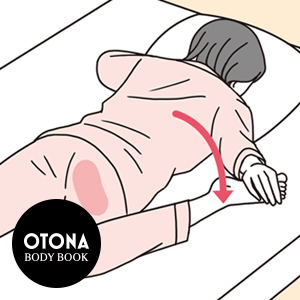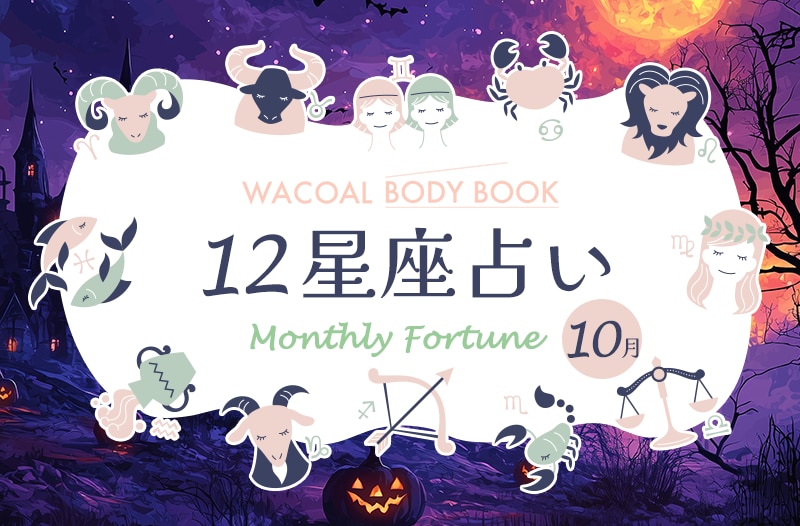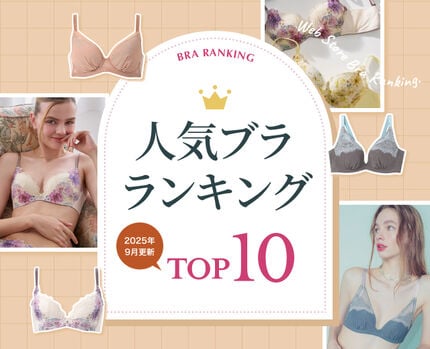- 新訳からだ辞典「パンツ一丁」
- 2019.12.25
今月のコトバ「骨休め」

カラダよりホネを休めたい
骨休めとは、骨を休めること。骨はカラダ全体を支える土台だから、骨を休めるといえば「全身を休めて疲れを癒す」という意味になる。「体を休める」よりも「骨を休める」のほうが、なんだか根本から力が抜け、疲れがとれそうな気がしてくるから不思議だ。模範的な例文をひとつ選ぶなら「温泉で骨休め」を挙げたい。骨の随まで(=からだの最も中心の部分まで)じんわり温まり、リラックスできそうなキラーフレーズである。骨には神経がないけれど、骨というカラダの重要な部位を使った慣用句は、文字通り骨身にしみるものが多い。
「骨が折れる仕事」「骨を刺す寒さ」「骨身にこたえる一言」「骨身を削って働く」のほか、「骨までしゃぶられた」などというコワイ表現もある。いささかネガティブな例ばかりで恐縮だが、このような「全身に訴えかけてくるような疲れやつらさ」を一気にチャラにしてくれそうなのが、「骨休め」という魅力的なコトバなのである。
骨休みをとろう
「骨休め」は「骨休み」ともいうらしい。日本国語大辞典によると、宮島資夫の『金』(1926)という証券相場にまつわる小説の中に「あなたと二人で呑気に骨休みでもやりますかな」という例文があるという。「骨休み」という言い方、かわいくないですか? 冬休みでもなく、春休みでもなく、骨休み。予定表に書き込んでみたくなる。「骨休め」と似た語感のコトバには「羽休め」がある。鳥が枝にとまって羽を休めることだが、人間にあてはめるなら、疲れているときに、カフェやバーに寄ってひと休みする感覚だろうか。実際、「とまり木」には「酒場などのカウンターの前に置く脚の高い腰掛け」という人間向きの意味もあるのだ。
骨休めには欠かせない、おいしい食事の中で使われる「箸休め」も、ゆったりとした味わい深い言葉だと思う。お口直しのために味に変化をつける簡単な料理のことで、たとえば、おしるこやぜんざいに添えられる塩昆布などは定番中の定番。最近では、食べている途中で飽きないように自分で調味料を加えて味を変えたり、別の味のものを食べたりすることを「味変(あじへん)」というが、これも、箸休めの新しい類語といえるかもしれない。
下着姿でおしゃれにくつろぐ
ところで、骨休めにふさわしいファッションといえば、もちろん下着である。フィンランドでは昨年、下着姿のまま、家でひとりでお酒を飲む「パンツドランク」というリラックススタイルが流行し、『Pantsdrunk』というおしゃれな本まで発売された。よく考えれば、あえてスタイルというほどのものでもないと思うが、フィンランドは、国連による2019年版の世界幸福度ランキングで、2年連続1位となった国。幸福度ランキング58位の日本で暮らす身としては、大いに気になるカルチャーだ。Wikipediaの「パンツ一丁」のページでは、世界のパンツ一丁の文化として、パンツドランクが次のように紹介されていた。「リラックスするにはパンツ一丁は最適な姿で、理解を深めた上級者であれば、パートナーや友人とのパンツドランクは互いの関係を深める助けになるという」。この記述は、イギリスの新聞『ガーディアン』からの引用である。
続く記述に「フランスのブティックでパンツ一丁の男性をマネキン役として置いたところ、女性客から高い評価を得たというエピソードもある」と書かれていた。このエピソードは以前、当コラムで紹介したことがあったなあ、と懐かしくなり、引用元を見たら、なんと当コラムの『今月のコトバ「パンツ」』にリンクが張られているではないか。というわけで、はからずもWikipediaに貢献することができ、とても光栄です。
それでは皆さま、年末年始はおしゃれな下着で、よい骨休めを!
相川藍(あいかわ・あい)
言葉家(コトバカ)。ワイン、イタリア、ランジェリー、映画愛好家。
好きなイタリア語は「スプーニャ(=スポンジ)」。ずぶ濡れになることを「スプーニャになる」といい、浴びるほど酒を飲むことを「スプーニャのように飲む」という。
からだをスポンジにたとえるなんてカワイイ。