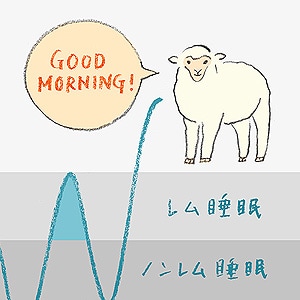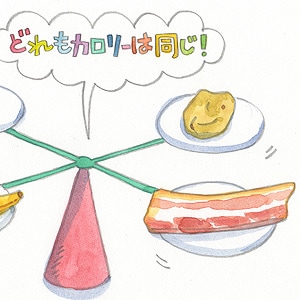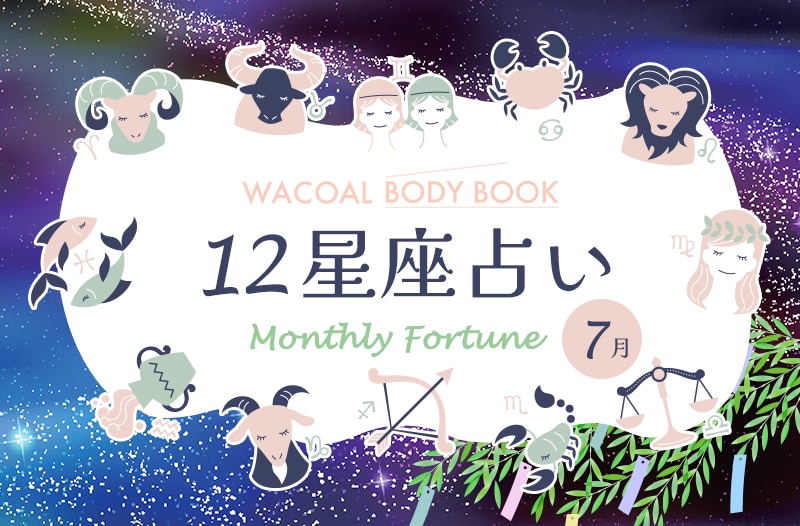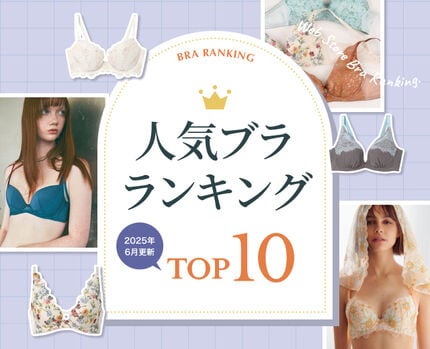- 新訳からだ辞典「パンツ一丁」
- 2019.07.31
今月のコトバ「衣(コロモ)」

夏はコロモを楽しむ季節
衣(ころも)とは、衣服のこと。ただし辞書には「古い言い方で、単独では普通使わない」と注があったりする。じゃあ、いつ使うの? まず思い浮かぶのは「衣替え(ころもがえ)」という言葉だが、最近は、衣を入れ替えたくない人も多いようで「衣替え不要の収納」が流行っていると聞く。世界的な異常気象の影響で、衣替えのタイミングはますます難しくなっていきそうだし。とはいえ、古語の世界では、年2回の衣替えは欠かせない。では、ここで問題です。衣替えの季節はいつでしょう。春と秋? 夏と冬? 答えはどちらもノー。「衣替え」は夏の季語だが、もう1回の衣替えは「後(のち)の衣替え」といい、秋の季語なのだ。したがって正解は「夏と秋」。「初夏と晩秋」と考えれば、なんとなく腑に落ちる。
衣の美しい用例としては「夏衣(なつごろも)」という言葉もある。うすし(薄し)、ひとへ(単衣)、たつ(裁つ)に掛かる枕詞だから、辞書を引くと俳句の例なども紹介され、華やかだ。しかし一方の「冬衣(ふゆごろも)」は「冬に着る衣服」と説明されるだけで、寒々しい。ちなみに「下衣(したごろも)」は下着、「夜の衣(よるのころも)」は寝間着のこと。いずれも風情があって、和菓子の名前のように聞こえる。
「衣」も「皮」もやめられない
実際、和菓子の世界には、小豆あんを白い砂糖生地で包んだ「石衣(いしごろも)」という半生菓子や、おはぎにまぶす「きなこ衣」や「ごま衣」もある。そう、衣には、食べ物を衣服に見立てたもうひとつの意味があり「揚げ物や菓子などの外面をくるんだり、まぶしつけたりするもの」を衣というのだ。海老天の衣が、海老の衣服だと思うと、海老も衣もだんぜん愛おしくなってくる。揚げる衣の王様といえば、ソーセージに串を刺し、ホットケーキミックスのような生地をつけて揚げたアメリカンドッグであろう。あのふんわりした厚さと食べごたえは他の追随を許さない。しかし私は先日、「ハットグ」という韓国式アメリカンドッグを初めて食べ、アメリカンなアメリカンドッグとの食感の違いに驚いた。米粉を使っているらしく、モチモチしているのだ。
その瞬間「これは衣ではなく、皮だ!」とひらめいた。ハットグのモチモチ感は、サクサク、フワフワな衣のイメージからは遠い。どちらかといえば「ギョーザの皮」や「生八つ橋の皮」の仲間ではないかというのが、私の見解である。引き続き、さまざまな衣や皮を食べ比べ、境界についての研究をかさねたい。
恋ゴロモをまとったあなたへ
天ぷらの衣について、ネット上で議論されているのを見た。ある天ぷら屋で、女性客が衣をはがして食べていたら、店主が激怒したというのだ。たしかに店主の気持ちもわかる。衣をはがすなんて言語道断。たとえ海老天の衣がするっと脱げたとしても、裸の海老を見て心を痛め、丁寧に着せ直して食べるのが人情だと思うから。ただ、この店の場合は衣がおいしすぎて、彼女は単独で味わうためにとっておいたのかもしれないな。と考えるほど、私は衣好きである。衣服の衣も好きだから、人間に生まれてよかったなと思う。皮膚(皮)の上に衣服(衣)をまとう人間は、まるでギョーザを天ぷらにしたかのようなゴージャスな存在だ。さらに「恋衣」(=常に心から離れない恋)をまとったりもするのだから、やめられない。ときには、あらぬ疑いをかけられて「濡れ衣(ぬれごろも・ぬれぎぬ)」を着せられることもあるけれど。
恋衣をまとった人に、耳寄りな情報をひとつ。夜の衣(=寝間着)を裏返して着ると、夢の中で好きな人に会えるんだって。少なくとも平安時代には、そう信じられていたらしい。「いとせめて 恋しき時は むばたまの 夜の衣を かへしてぞきる」という小野小町の歌がある。どうしようもなく恋しいときは、寝間着を裏返して着ようという歌だ。夜の衣の表面には、恋しい人の香りが残っているのかもしれず、セクシーな妄想をかきたてる衣の歌である。
相川藍(あいかわ・あい)
言葉家(コトバカ)。ワイン、イタリア、ランジェリー、映画愛好家。
好きなイタリア語は「スプーニャ(=スポンジ)」。ずぶ濡れになることを「スプーニャになる」といい、浴びるほど酒を飲むことを「スプーニャのように飲む」という。
からだをスポンジにたとえるなんてカワイイ。