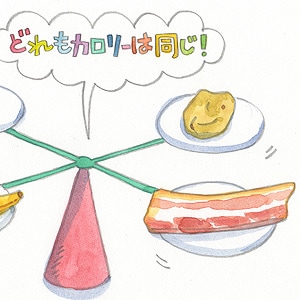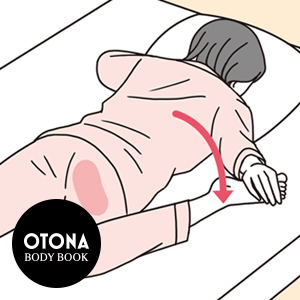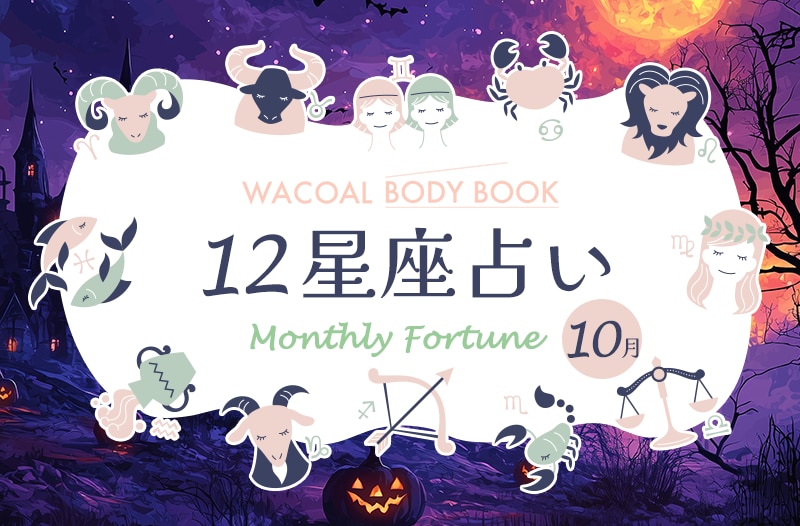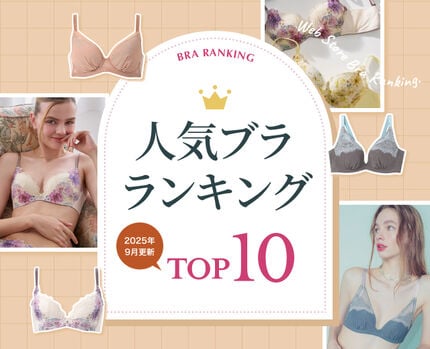- 新訳からだ辞典「パンツ一丁」
- 2019.02.27
今月のコトバ「名は体!」

昔のカラダに戻る方法
「名は体(たい)を表す」ということわざがある。「名前は、その中身や実体を表している」という意味だ。つまり「体」とは「本当の姿」のこと。たぶん、あなたのまわりにも「美しい美子さん」や「明るい明さん」がいらっしゃることと思う。手元のことわざ辞典には「名は体を表すというが、オネストさんはとても正直な人だ」というひねりの効いた例文があった。オネストさん、日本でひどい目にあっていないかと、やや心配になってくるが。もちろん、名が体を表さないケースもある。自分の名前がしっくりこない場合は、改名する手もあるが、手続きなど面倒なことも多いと聞く。好みの芸名やハンドルネームをもつことは、ひとつの「体」に縛られず、気軽に気分転換するための有効な方法といえるだろう。また一方では、他人がつけてくれる愛称や呼び名、ニックネームというのもある。懐かしい愛称を振り返ることで、忘れかけていた「本当の自分」を再発見することができるかもしれない。
日本で生まれ育ったイタリア人男性、オネストさんの場合なら、これまで「オネストくん」「オネッチ」「オネ」「オネちゃん」などと呼ばれてきたに違いない。今は正直者の社会人「オネストさん」として愛されている彼も、中学の同窓会で「オネッチ」と呼ばれた瞬間、親や教師を困らせた悪ガキ時代に戻ってしまうのだろうし、高校時代のバンドメンバーに「オネ」と呼ばれようものなら、すぐに当時のレパートリーを振り付きで歌い出してしまうだろう。
愛称から始まる愛もある
特別な愛称で呼ばれたことのない人も、身近な人を愛称で呼ぶ楽しみというのはある。仲のいい友だちをドラマチックな愛称で呼べば、毎日がドラマチックになるし、あまり好きではない人を試しに好みの愛称で呼んでみれば、だんだん好きになってくる(こともある)のではないだろうか。そんなふうに考えたのは、友人のM子が、会社の同僚には言えない「上司の悪口」を私にぶつけてきたとき、その上司の愛称が「ももっぺ」だったことを思い出したからだ。皆が上司をそう呼んでいるわけではないらしく、M子だけが心の中で彼をももっぺと呼び、毒づいていたのである。M子が「ももっぺがさあ」と憎々しげに言うたびに、私はおかしくてたまらなかった。ちっとも悪口に聞こえないどころか、むしろ好きなのでは?というレベル。
「もものようなほっぺ」や「もんぺの似合うふともも」を連想させる「ももっぺ」は、可愛くて温もりがあり、どうしても愛が感じられてしまう。悪役の呼称としてはふさわしくない。そう私が指摘すると、M子はすぐに「ももっぺ」を「あの野郎」に変えて話を続けてくれたが、M子のハニーボイスで発音される「あの野郎」は、やっぱりどこかいい人っぽいのであった。そのうちM子が「ももっぺと結婚する」と言い出しても、私は驚かないだろう。
ときめきのボディサイズ
最近、すてきな万年筆をいただいた。ボディの色名がフランスワインの二代産地のひとつ「ブルゴーニュ」なのである。解説を読むと、万年筆の書き味の熟成をワインの熟成のようにとらえ、ふさわしい色の試作を重ね、丹念に成型したという。ブルゴーニュという名前が、ボディカラーと万年筆の本質を表現しているのだから、まさにダブルの意味で「名は体」である。この万年筆で美しい文字(自分比)を書いていたら、「名は体」の美しい例をもうひとつ思い出した。フリガナを意味する「ルビ」である。かつて英国では活字の大きさにダイヤモンド、パール、エメラルドなど宝石の名前をつけており、ルビーという5.5ポイントの活字が、日本でよく使われていたフリガナの大きさに近かったことから、フリガナを「ルビ」と呼ぶようになったそう。
文字のサイズを宝石にたとえるなんて、なんてロマンチックなんだろう。人間のボディサイズにも、ロマンチックな名前をつけてみたい。とりあえずS、M、Lをサファイア、ムーンストーン、ラピスラズリって呼ぼうかしら。
相川藍(あいかわ・あい)
言葉家(コトバカ)。ワイン、イタリア、ランジェリー、映画愛好家。
好きなネット用語は「パンくずリスト」。自分が今どこにいるのかを示す階層表示のことだが、ヘンゼルとグレーテルが森で迷子にならないよう通り道にパンくずを置いていったエピソードに由来すると知り、キュンとした。